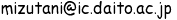参考文献情報は必須である
文芸作品のように著者の想像力「だけ」によって書かれる場合を含めて、私たちのアイデアや思考は自らの経験や先行事例としての文書または人との会話などを資料(source)としている。 こうした多層に折り重なった経験が刺激やインスピレーションとなって私たちの思考を駆動させて、私たちの考えを発展させている。
論文や報告書においては、以下の諸点がが強く求められている。
- 文書作成で利用した資料すべてが参考文献としてリストしてある
- 文書内の何処でそれら資料を参照したかが明記され、さらに
- 参考資料の何処をどのように活用したか
したがって、文書の末尾に参考にした資料をまとめて列挙するだけでは全く不十分である。 何故、上記のようにしなければならないのか、その必要性を含めて理解することは大学生が書く文書作成の出発点である。 これらの配慮がない文書は盗用(または剽窃 plagiarize)の誹りを受けることになるやもしれない。 全ては著者の責任である。
参考文献として列挙する資料としてどのようなものが相応しいのかは、文書の発表時には深く考える必要がある。 文書の完成に向けて、そもそも参考文献として記載すべき情報が整備されているかは繰り返し慎重に検討する配慮が欠かせない。 文書を仕上げる際には
- 文書に「求められる参考文献情報とは何か」が配慮されている
文書作成のマナー
参考資料の全てを明らかにして、その利用箇所を文書中でその都度正確に記すことは、文書作成のマナーであると同時に、文書の読者が求めていることである。 読者は著者の思考を追いながら、そこで展開されている主張を吟味し批評する。 実験報告であれば記載されているデータが正しいかどうかを追実験できるように書かれていていなければ、報告されたデータを信ずるに足りないと判断する。 参考資料の誤用や資料著者の主張を誤解した記述があれば、読者の信頼を失い文書は正しく読まれることはないだろう、・信頼される文書は一次資料から
参考にした資料が文書末にリストされているだけでは十分でない一方、文書作成の 文言の調査や気づきや考察のきっかけを与えた情報を参考資料とするのは原則として不適切である。
たとえば、政府の政策を新聞記事で知ったとき(多くの事実情報は新聞やTVから得ていることは事実だとしても)、その政策についての参考文献情報を新聞記事に求めるのは妥当だろうか。 報道記事は報道各社の報道姿勢によって大きく違っている(これは当然のことでジャーナリズムの意義はそこにある)。 さまざまな数値(気象データから経済指標まで多様にある)が紹介されている新聞雑誌の記事を参考文献情報とすることは適切だろうか。
このように、その記事が文書作成の契機や知識を与えることになったとしても、だからといって論文や報告書の参考文献とするには「確かさに欠けている」。 紹介記事がそのまま読者の信頼を得る文献情報になるとは言えない(「フェークニュース」という残念な言葉も生まれている)。
参考文献とするには綿密な調査が必要
作成する文書とそれを書いた著者が信頼されるためには、まず参考文献情報が信頼される情報となっている必要がある。 読者が著者の主張や結論に納得出来ない場合であっても、取り扱われた参考資料の有用性をもって著者への信頼と敬意、関心が惹起され得ることを知っておこう。
伝聞や引用の「ネタ元」となった根拠情報や信頼に足りると大多数が認める「権威ある」情報を一次資料(原典:primary source)という。
論文やレポートにおいて「有名」新聞の記事を参考資料として挙げたとしても、読者に根拠が示されたと言い難く、場合によってはそうすることによって文書著者への信頼性を損なってしまうことになることがある。 報道記事が依って立つ「真の情報源」を追求・調べあげて、それを(またがその経過を)参考資料として明記するのである。 その調査事態が容易でないこと`も少なくないが、それだけの価値はある。
Wikipedia「資料」によると、「資料をその独自性および生データへの近さにより、一次資料(primary source)、二次資料(secondary source)、三次資料(tertiary source)等と分類することが多い。」とある。
次のように、一次資料と二次資料を定義している。- 一次資料は、元の文献などそのものであり、原典ともいう。
- 二次資料は、それらの一次資料を編集して掲載した資料。 資料の分類は学問分野によって多少異なる。例えば、明治時代の文学を研究している文芸批評家にとっての一次資料とは詩や小説そのものである。他の文芸批評家が書いた評論は二次資料となる。また、新しい抗ガン剤を求めて研究している医学者にとっては実験結果や患者の治験記録を発表した論文が一次資料であり、それらの文献の一覧は二次資料である。
三次資料はさらに二次資料を編集して掲載した資料ということになり、二次、三次となるにつれて原点から遠ざかり、それにあわせて信憑性や信頼性が低下していく。
真似ることは大切〜実際の論文で資料の取り扱いを知る
以下の論文で内容はともかく、それぞれの論文で参考情報がどのように扱われているのかを精査し、そのスタイルを真似て論文を書いてほしい。
 田越秀行, 中村卓史 「重力波の初の直接検出とその意義」
日本物理学会誌 71巻4月号, 210-211ページ, 2016年
田越秀行, 中村卓史 「重力波の初の直接検出とその意義」
日本物理学会誌 71巻4月号, 210-211ページ, 2016年
- 2017年ノーベル物理学賞が授与された業績 「LIGO検出器への決定的な貢献と重力波の観測」(R.Weiss、B.Barish、Kip S.Thorne)の意義についての開設。
 原発震災──破滅を避けるために (PDF)」岩波書店(『科学』1997年10月号)
原発震災──破滅を避けるために (PDF)」岩波書店(『科学』1997年10月号) G. Perelman, "The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications", arXiv (2002 Nov.11)
G. Perelman, "The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications", arXiv (2002 Nov.11)- 1904年に出された数学最大の未解決問題の1つだったPoincaré予想を解いた3つ論文の先頭論文。 専門の数学者たちによる理論の検証に2006年までかかり、2006年のフィールズ賞が贈られた(本人は受賞拒否)。