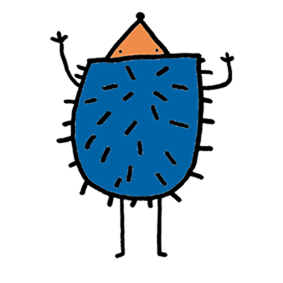
図書館あちこち
これは1997年12月から1999年4月まで、『大東新聞』に掲載したエッセイです。付け加えなければならない部分、訂正しなくてはならない部分、いろいろありますが、今は取り敢えず、掲載された段階のままでここに載せておきます。……と、いうのも当時これを読んだ学生が「すごく面白かった」と言ってわざわざ尋ねてきてくれて、後輩に教えたらしく、「読みんでみたい」という要望が、今尚、ぼくのところにやって来たりするためです。今後は、しかし、このサイトは「日本の図書館・世界の図書館」というようなサブタイトルで、興味深い典籍を蔵する図書館などについて記し、図書館サイト・マップにして行きたいと考えています。
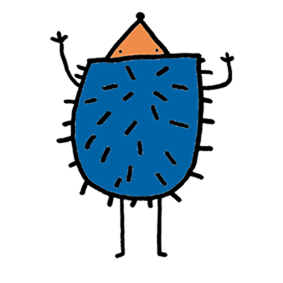
図書館あちこち(一) ナメクジから餞まで
人生に偶然がないとしたら、失恋もまた、ぼくを外の世界へ引っ張り出してくれるために用意されていたものだったのかもしれない。ナメクジの大群の大移動を夜中に見て電話をかけきたぼくの恋人が言った言葉。「もう、わたしたち、ダメみたい。いい友達でいましょうよ」そして、そんな言葉を信じたこともまた、偶然ではなかったのだ。バカヤロウ。他の男とイチャイチャしやがって。こうしたキッカケから、いつのまにか、ぼくはシワシワ、ショボショボ、グジグジに凋んだ自分の心を癒すために、勉強へと触手をのばして行ったのだ。だって、その時、ぼくは既に四年になっていて、しかし単位は全然足らず、どう頑張っても卒業まであと二年は必要という状態。親はひっきりなしに夜中、朝方と電報を打って来て(ぼくの部屋には電話がなかった…電話の音、嫌いだったし…)もう大学は止めて田舎に帰って来いと言う。 …「就職」。親父の口から出るその言葉を聞くたびに。…田舎に帰って、就職すると…朝九時から夕方五時まで会社にしばられて、そのうちまた恋に落ちて、そして結婚して、子供が出来て…家でも建てて…そのうち、いつのまにか、いつのまにか停年になって、孫かなんかをあやしながら、…いつのまにか死んでしまう…そんなイメージが頭の中にモヤモヤとナメクジが塩に融けるように湧いてくる。あああああああ、そんなの嫌だ。絶対嫌だ。死んでもイヤだ。 ぼぼぼくには、ままままだ、東京にいてやらなきゃなななならないこここことがあるんです。…と、親に言ってもそんな言葉は信じてくれない。「本ばっかり買って、何やってんだ。危険思想でも植え付けてるんじゃないだろうな」 実際、本ばかりを、ぼくは買いあさってアパートの大家からは出ていってくれと泣きつかれていた。部屋中の壁と空間を埋める十六本、八段の本棚はマルクス、レーニンの全集か ら岩波の数学、哲学歴史講座、ヒッタイト語、ラテン語、サンスクリット語等々の辞書、オクスフォードの英語大辞典、大漢和辞典、卒論のテーマに選んだ老子に関するものも含めて明版や清朝の版本、江戸の刊本でふさがって、雪崩状態をおこし、歩くたびに、床はミシミシと音を立てている。 そして、机の上には千五百枚を越えてまだ書きかけの卒論…。 「だだだ大学院へ行く予定で勉強も頑張っているから…」 と、その年と、次の年と九州大学の大学院を受けたものの、結局、九大に縁はなく、合格することは出来なかった。しかし、これもまた、失恋と同じ。物事を明るく考えれば、なんとか世の中は面白くすることが出来るのだ。ぼくは、跪いてアパートを図書館のごときものにはしないでくれ、と頼む大家に礼を言って引っ越しをし、大東の大学院に籍を置いて、指導教官である河崎先生から紹介された神鷹先生(帝塚山学院大学、また本校の非常勤)と古本屋をぶらつき、学問の喜びを吹き込まれ、そして、神鷹先生から紹介された林望師匠(現東京芸術大学)について、駒込の東洋文庫の書庫に明けても暮れても引きこもり、二年あまり奈良時代から江戸の初期までの間に書写、あるいは出版された書物の解題に没頭した。このあたりの哀しく辛い経緯については、林のおっしょさんが本に書いている(何という書名だったかは失念)。…だが、師匠のお陰で、ぼくは、一昨年亡くなってしまわれた亀井孝大老師に最後の弟子として認められ、東洋文庫の研究員にして頂いた。…その時には、既に、林師匠とケンブリッジ大学東洋学部のピーター・コーニツキ氏から依頼されて、ぼくはしばらく(何年いるのかという計画は全くなかった)『欧州所在日本古書総目録』プロジェクトのために、ヨーロッパ各地に所蔵される日本の古書(もちろん、ぼくがやりたければ、中国、韓国の書物も含めながらという条件で)を調査することになっていたのだ。亀井の恩大師は、ぼくの旅立ちに対して『古文真宝』の古活字本を餞て下さった。「山口、もしも、金がなくて、しかし、どうしても日本に帰って来ないといけないことがあったら、これを林に売れ、市価の三倍で」という言葉を添えて。この書には仁和寺心蓮院の蔵書印が押してある。「もしも、山口が帰って来た時に、オレが生きていたら、もう一つ、ぼくの別の蔵書印を緑の印泥で押して上げよう」と。だから、この本にはドイツの髭文字を使った老師らしい雅致のある「K Takashi 蔵」という朱の蔵書印が一顆だけ寂しくついている。 …とにかく、欧州に発つに際して一度閉館したぼくの個人図書館に、旅立ち前に入った書物はこの『古文真宝』。これを最後にして、ぼくはイギリスへと向かった。既に八年前のこと。…とにかく、「図書館あちこち」…この度はその前座。さてさて、次回から欧州の図書館へと参ることにいたしましょう。
図書館あちこち(二) ケンブリッジ大学図書館
ケンブリッジ大学付属図書館に所蔵される日本の古書については、既に、林望、ピーター・コーニツキの共編で『Early Japanese Books in Cambridge University Library』(邦題『ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録』)と題してCambridge University Pressから出版されている。この画期的革命的曠古の目録は、ケンブリッジ大学所蔵国書コレクションの全貌を知るばかりでなく、書誌学に新たな息吹とその学問の方法、方向性を見事に描き出した。ケンブリッジに着いてぼくがやったことは、この目録(ぼくが行ったころには、まだ、『目録』は校正の段階だった)に照合しながら、現物を入念に再調査することだ。全二千五百六十九タイトルの書物を、タワーと俗に呼ばれる、南北に伸びる開架式図書館の真ん中に立った書庫に小さな古いエレベーターで毎朝、登って行って調べる。ケンブリッジの蔵書の中で、一番古いものは、何と言っても奈良時代、神護景雲二年(西暦七六四年)に称徳天皇の発願によって制作され、奈良の十大寺に安置された『百万塔陀羅尼』の五本、完全な揃い。これは、東洋文庫にだってそのうちの三本の陀羅尼だけがあるだけで、揃いを拝むことが出来るのは、世界中でも静嘉堂文庫とケンブリッジだけ。それから、面白いのは、これは特にぼくの専門ではないが、所謂八文字屋本。林師匠の詳細な分類目録に当たりながらこれをもう一度、再調査する。岩波文庫でも翻刻されているが、ケンブリッジ大学の蔵書は、明治時代の外交官アーネスト・サトーが、日本からの帰国に際して、イギリスに宛て送ったもの。彼は、自分の蔵書をアストンという若い研究者に委託して、それが大学の日本関係蔵書の基となったのだ。サトー、アストン旧蔵、そして林師匠が手を触れた本をもう一度、自分の目で目録を取りながら触っていると、いつのまにか、どこからか漂ってくる海の匂いに、ぼくは包まれていた。遠い遠いところからぼくの方へ向かって吹いてくる風…それがなんだったのか、ぼくには未だにわからない。横浜か、或いは古い埃にまみれた長崎の港の匂い…しかし、この追調査をすることによって、ぼくは、書誌の真髄に触れることが出来たような気がする。「書誌学者はね」と、林御師匠は、東洋文庫のカビ臭い日本研究室で目録を取りながらよく言ったものだ。「知らないことがあっても、『知らない』と言っちゃいけないんだ。知ったかぶりをするということとはもちろん違う。知らない、見たことがない本があっても、そこから的確に核心を見抜く力を養わなきゃいけない。それが書誌学者の力というものなんだよ」と。ぼくらの机の上には、室町、南北朝の所謂五山版が山積みになっていた。「ヨーロッパの図書館で何が出てくるかわからない。たった独りで、誰にも相談することが出来ないからって、出てきた本が分からないんじゃ、プロとは言えない」。タワーの八階でひとりページをめくる机の横で、林さんがぼくにくれた『東方年表』がヒラヒラと風に揺れている。その最後のページ「富士、富士、富士、富士よ。ぼくに明日はあるか・新幹線にて」。鉛筆で走り書きされた師匠の字…調査で京都に行った帰りに新幹線の中で書かれたもの…。様々な思いが、古い江戸の刊本のページを開く毎にチリヂリになって飛んで行った。 三月、ぼくがケンブリッジに着いたばかりの頃に咲き始めた図書館の桜は、ぼくの追調査が済んだ五月の末まで咲き続けて、そして緑の葉に覆われた。いづれ、その中、調査に行くべきことになっているベルリンの国会図書館所蔵の古書の下調べもやらなきゃならない。エヴァ・クラフト女史が作られた「Die Japansammlung der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz」を岩波の『国書総目録』を頼りに各図書館の所蔵目録と首っ引きで調べながら、版式と、出版書肆とを比較しつつ、刊、印、修の違いを推定する。それから、既に、故反町茂雄氏が『Japanese Illustrated Books and Manuscripts of the Chester Beatty Library Dublin Ireland』(邦題『チェスタービーティーライブラリー蔵日本絵入本及び絵本目録』)と題して出版されたダブリンにある書籍についても、同じことをやらなきゃならない。やらなきゃならないことは山ほどある。そして、やりたいことも、もちろん。昼休みには、ぼくは、昼飯を喰いながら、アーカイヴのエリザベス・リーダムグリーンからラテン語を習い、夜、書庫が閉まってしまってからは、サウス・ウイングの四階にある、日本事務室にあるコンピューター(今ではインターネットでどこへでもアクセスすることが出来るようになったけど、その頃はジャネットというシステムでイギリスの大学は繋がれていた)の前に座って、言語学関係の資料を補漁した。ある本が出版、或いは書写されるに際し、それを校訂し、書き、掘って作るに当たった人間のもつ音韻体系は、本に反映するに決まっている。ぼくは、そこのところが見たいんだ。ケンブリッジ…朝、起きると、いつも、鴨が窓をコツコツと嘴で叩いて、ぼくに餌をねだりに来たっけ。…来年(一九九八年)の春には新しい図書館の建物が南(?)ウイングの端につくられているという。日本関係の書籍は、全部そこへ移動するとか。
図書館あちこち(三) アイルランド・ダブリン、チェスター・ビーティー・ライブラリー
六月になっても、ケンブリッジには、当然のごとく梅雨はやって来なかった。別にジメジメした雨を待っていた訳では、もちろんない。しかし、カッと暑い日が何日か続いてイヨイヨ夏かと思うと、ストーブを入れないといけない程の寒さがぶり返しにやってきて…ということが何回か繰り返され、その中、七月に入ると、ケンブリッジ大学図書館の庭に美しく輝いていた芝生たちは、暑さでボサボサと茶色に変色し、西側から順を追って次々に枯れて死んでいった。…だから、と、言うのではない。ぼくは、前触れもなく、コーニツキ氏が予約した「一週間滞在可能。変更不可」とスタンプが押された飛行機のディスカウント・チケットを手に、ダブリンに発った。今世紀初頭のアイルランドの大富豪(銀行か何かを経営していたらしいが、この人の伝記なんかについて詳しいことはよくぼくには分からない)チェスター・ビーティーが個人で集めた絵入り本、全二三〇点の調査をするためである。「二三〇点なんて、一週間で終わるわけないじゃん。しかも、発つのは土曜日。土日って図書館閉まっているわけだから、実際に調査が出来るのは五日。五日で二三〇点…」と、ぼくは、ピーターに言う。「そないなこというたかて、これしか、チケットあらへんやん」以前京都に長く住んだことのあるピーターは、大阪弁と京都弁をゴチャゴチャにした日本語で言う。「どうして、ちゃんと帰りの日にちを変更することが出来るチケット買わないのかな」「金ないやん」ただ、この一言で、会話は終わってしまう。「飯とかホテルとか、そんな必要経費はどうなってるの」「出るかもしれへんし、出えへんかもしれへん。まあ、立て替えといてや」林のおっしょさんから言われていた通りだ。ピーターは、自分の食事代とか、ホテル代は経費から出すのに、人の分については絶対出さないよ、と。この辺りは、もしかしたら、大阪京都辺りで日本語と一緒に勉強したことなのかもしれない。そして、当然、ピーターは、ケンブリッジから程遠くないところにあるスタンステッド空港にさえ、出発の当日、ぼくを送ってはくれなかった。「チェスター・ビーティーには、潮田さんという日本人の女の人がいはるから」「いはるていうたかて、二三〇点、しかも、室町時代後期から江戸時代初期にかけて作られた奈良絵本が八〇本近くあるんやで。その上、反町さんの目録を見ると、南北朝の大般若波羅密多経、慶長刊の古活字『君臣図像』、菱川師宣のものなど、見事なコレクションが揃うてまんがな。それをたった五日でやるなんて…」と、そんなことを言ってみても始まらない。やらなあかんもんはどないなことをしてもやらなあかん…。 ひっそりと静まり返った住宅街の奥、こんなところに図書館なんてあるものか…というような場所に、バラの蔓に囲まれたチェスター・ビーティーは、こじんまり、畏まって建っていた。開館前に風呂敷を下げてやってきたぼくを、守衛のおじさんが、うさんくさそうな目でジロジロ見ている…風呂敷の中味は、書誌の七つ道具、ものさし、『東方年表』、書き込みに書き込んで、ボロボロになった『内閣文庫国書分類目録』同じく内閣文庫の『漢籍分類目録』、蔵書印を読むための『印文学』と『篆楷字典』、調査すべき本と比較検討するために用意した書影等々。…そんなものがなくては仕事にならないのだから、ぼくは、本当なら、フェリーかなんかに乗って、自分の車でダブリンまで来たかったのだ!! それはそれとして、しかし、反町さんの目録(昭和五四年、弘文荘発行)の序文にも書いてあることだが、サー・チェスター・ビーティーという人は、世界中の古い美しい写本、刊本を金にあかせて手当たり次第蒐集したらしく、行ってみると、そこには、『目録』序文に書かれた以上の金襴豪華、絢爛無比、有難迷惑なほどの古籍が展示され、閲覧できるようになっている。インキュナブラは掃いて捨てるほどあるし、十六世紀初頭イタリア式箔押し装丁のなんだかよくわからないが、ローマ字にギリシャ語を並列して書かれた絵入りのかわいい本なんかも、書庫には、ビッシリ詰まっている。 最後の最後の日のギリギリの時間まで日本の古書の目録を必死になって取っている脇で、図書館の東洋部長、チャップマンさんが、巨大な胸を机に押しつけて、ノベツマクナシにぼくに書誌のことについて質問を浴びせかける。「…ミスターヤマグチ、あなたは、中国の専門だって訊いたけど、最後にもうひとつ、教えて欲しいことがあるの。この本のことなんだけど…」チャップマンさんの胸には帙に入った巨大な本…ゲッ!!本物、正真正銘、東洋文庫の書庫で見たことのあるのと、寸分違わぬホホホホンモノの『永樂大典』…明の永樂帝が解縉という人間に命じて作らせた二万二千八百七十七巻の大作の類書。刊行されることはなく、一〇八人の謄写官を選び、嘉靖三六年(西暦一五五七)から隆慶元年(西暦一五六七)まで掛かって、これを一日に三葉と決めて、書写させたとか。明末に焼け残った残巻が世界中に点々と散在し、それらのほとんどは、既に影印本などで紹介れている。ししししかし、ここにある『永樂大典』、これは未発表、未公開、所在が知らていない巻やんけ!!と、日本の古籍の目録を取りながら、胸をドキドキ高鳴らせつつ、後悔先に立たず、ぼくは、未調査の和書何点かを残して、次回のダブリン訪書を企てつつ、帰路についたのでありました。
図書館あちこち(四) ロンドン大学、そして、ヴィクトリア・アンド・アルバートミュージアム
ダブリンからケンブリッジに戻ってみると、ピーターは、ぼくを牛馬の如くコキ使うつもりなのか、次に調査を行うべき図書館のリストをぼくの机の上に置いて学会に出かけてしまっていた。「ヘーイ、ピーター、ダブリンの経費は何時返してくれるんだよー。月給の三分の一は家賃で消えてしまっちゃうんだから」 今度は電車で毎日、ロンドンまで通えっていうのかい?街の中心を軸にぼくの家から全く正反対の場所にあるケンブリッジの駅まで行って朝七時前の電車に乗って一時間半、ロンドン大学までは歩いて二〇分。それはいいけど、ヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムまでは、地下鉄に乗らないといけないじゃない。風呂敷を抱えて、ラッシュの中を毎日、往復するなんてさ、そんな、そんな…そんな無茶言わないでよ。地下鉄ってぼく、東京にいた時から大嫌いなんだから。とゴチャゴチャ言ってみても、先方ではぼくが来るのを待っているという。 「ロンドン大学所蔵の和書については、浄瑠璃本、丸本と床本を除いて林さんが目録を作っているから、これと残りの和刻本漢籍…ヤマグチ君が専門にするところを中心にやってよ。それが終わったら…」「それが終わったら…なに?」「…ベルギー。いよいよ大陸へ進出でんがな!!」 てなわけで、ロンドン市内のラッシュを避けるために、ぼくは、朝六時に家を出て高速を飛ばし(と言っても、ぼくの車はシトロエンの二CV、どんなにアクセルを踏んでも最高九〇キロしか出ないのだけど)先ず、ヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアム。裏口の守衛さんに許可証つきバッチをもらってNational Art Library and Far Eastern Collectionsを管理しているマリア・ホワイトという名のちっちゃくてポッチャリかわいい司書のお姉さんから、イギリスらしくナミナミに注がれたまずいコーヒーをありがたく頂いた後、日がな一日、昼食も取らず、ミュージアムを巡って歩く見学者の頭上の回廊に雑然と並べられた本の目録を、次から次に取って行く。マリア(呼び捨てにするのは、ぼくらは、このあとすっかり仲良くなって楽しくご飯を食べたりする間柄になったから)は三〇〇タイトルというけど、あくまでそれは彼女の概算。二週間かけて三〇〇タイトル終わっても、まだ、半分にも達してはいない。一時になると、彼女がやってきて一緒にごはんを食べに行こうよと、誘うのだが、ぼくにはそんな暇がない。その場で目録を取り終わっても、書誌の仕事が終わったわけじゃないのだから。読めなかった蔵書印は、篆書の辞書を使って判読しなきゃならないし、参考書に当たって完全に刊・印・修がはっきりするまで他の本と比較したりしなきゃならない、等々。いつまでたっても調査は終わってくれはしないのだ。 ケンブリッジ大学やチェスター・ビーティーに比して見れば、ヴィクトリア・アンド・アルバートには、これと言って特筆すべき本はない。強いて言えば、菱川師宣や西川祐信の絵本なんかが保存状態悪く、雑然と、バラバラにあるくらい。あとは、時々、サトウの蔵書印が押された本が出てくるだけだ。どうしてこんな所にサトウの旧蔵書があるのか、それは、マリアが何かに書いている。五時に閉まってしまうミュージアムの調査を終えると、その足で、ぼくは、夜九時まで開いているロンドン大学(School of Oriental and African Studies, London、通称SOAS)に直行だ。ここは、和刻本も清朝の本も明版も洋装本と一緒になって(惜しいことに宋元版はなかったけど…しかし、あったら、とっくのむかしに盗まれてしまっているね!)全部開架式の書架にABC順に並んでいる。ほとんどは、一度、ぼくが東京で目録をとったか、或いは自分の蔵書として持っている本ばかり。私蔵の長沢規矩也博士の『和刻本漢籍分類目録』を繙けば、そこには現物を手にとって博士の調査を確かめ質して書き入れたぼくの調査ノートがある。 しかし、このSOAS…英文科かなんかを出て、この大学へ行くひとも多いのかもしれないけど、ここはアフリカ人とアジア人と、中にイギリスやフランスやドイツからやって来たヒッピー風の学生が混然一体となって、七〇年代の雰囲気みたいなものに包まれていた。ケンブリッジなんかじゃ絶対に見あたらない左翼バリバリって感じの扇動的ビラが学生食堂には掛かっていたりして。…、だけど、…それにしても…生きていたとしたら五十歳くらいになるのだろうか、…鼻の下に髭を蓄えたブライアン・ヒックマン氏…、変な学生に邪魔されずに仕事が出来るようにと、ぼくにいろいろ便宜を計ってくれたSOASのキューレーター、彼はぼくがフランスに渡ってしばらくしてから、突然亡くなった、と聞いた。
図書館あちこち(五)閑話休題…書誌のことなど
「ヤマグチさん、中国のことやってるんでしょ?なのに、どうしてヨーロッパ?」と、ぼくは、ショッチュウ、人に訊かれる。どうせ、人ごとじゃないか、好きなようにやっているだけだよ、と思うけど、そんな風にも言えないから、とりあえず、ぼくは、こう答える。「フランス、イギリス、ドイツ、そしてロシアには、敦煌で発見された七世紀ころからの文献が沢山、所蔵されていますから」と。でも、ぼくは、そう言いつつ、本当は別のことを考えている。「中国学、別の言い方をすれば、シノロジー、というのは、ヨーロッパ、特にフランスの人文科学を打ち立てた精神無くしては、出てこななかったのじゃないかな」. 勿論、中国学っていうくらいなんだから、中国自体にその学問の源流はあるわけだし、日本だって、奈良時代からずっと、明治の開国に至るまでの長い間、中国文化の影響を受けて、当然、中国から入ってくる学問を日本としての方法で解釈し、咀嚼してきたし、そういう意味では日本にだって日本らしい方法での中国学っていうのはあった。そして現に今でもそんな風なやり方で研究を続けている人だっている。でも、と、ぼくは、思う。…自然科学とか、社会科学系統の中国に関する研究分野はさて置いて、人文科学、しかもぼくが専門としている文献学という分野に於いて、果たして、ヨーロッパ的な方法と精神がなくて、それが学問として日本で、或いは中国で育っただろうか、と。 物事を相対的に見ることが出来ない人たちがいる。例えば、本を見るとすぐに、これは「いい本」、これは「悪い本」と、いうレッテルを貼ってしまう人。「悪い本」は、その人にとってゴミ同然。そういうレッテルを貼られると、もう「悪い彼」は振り返ってさえもらえない。「宋版(宋の時代に出版された本)はいい」という風潮に乗って、こういう人は宋版ばかりを追いかける。そして、「日本の旧鈔本がいいよ」と、聞けば、それに便乗してドンドンドンドンそっちの方へ行ってしまう。何故、如何なる点で、それがいいのかということを、自分で考えることもしないまま。 ねえ、学問って、そんなもんじゃないでしょ?本は、単にニュートラルな資料なのですよ。うまく使うことが出来るかどうかは、使う人の力量によるのです。 …でも、はっきり言って、中国でずっと行われてきた学問って、なんだか、それに類する嘘ハッタリっぽいところがたくさんあるんだよね。自分の先生の説を後生大事に守って言いたいことも言わないとか、孫引きに孫引きを繰り返して、何処に本当の出典があったのか分からなくなってしまってしまったりとか。贋物をさもホンモノらしく見せてごまかしてしまうとか。例えば、本に関することで言えば、誰かエライ先生が「この本は北宋版(実際にはそんなものはほとんどない)だぞ」と、言えば、このエライ先生の言葉を信じちゃって、誰も楯突かない。そうして、この本は有名になって、写真版が作られる。エライ先生のご意見を固守するために、書誌的な調査を阻むような小細工まで加えられて。するとさ、いつのまにかそれが底本となって通行する。みんな、これを北宋版だと信じたままね。そいで、人はその本を使って論文を書いたりするわけでしょ?それが、でも、もし、音韻に拘わるような問題を含んでいたりしたらどうするんだろ。提示される問題は、既にこの時点で混乱してしまうんじゃないのかな…。 だから、「刊・印・修」(毎回この用語をぼくは使っていますが)ということが古籍には必要になるのです。簡単に言ってしまえば、「刊」とは、発行された年月日、「印」とは、それが紙に刷られた時のこと、そして「修」とは、本に修理或いは補正が加えられたことの有無とその時代。昔は木版というものを使って本を作ったわけだから、版木が残ってさえいれば作られた時代から隔たってからも、印することが出来たし、一枚だけ版木が足りなければ、後でその部分の版木を彫って足したり、間違っていたりして字を変えてしまいたいところがあれば、部分的に版木に修を加えることも出来たんだよね。詳しいこと、問題になるようなことは避けるけど、覆刻とかそんなことがあって、この刊・印・修が三面記事のごとき複雑怪奇さをもって、現れてくるのです。本屋の利害関係なんかも加わってね。…特に、贋物作るのって、中国の人たちの得意とするところでしょ?古ければ古いほど骨董的な価値も付加されて値上がっていく書物たち。ホンモノとニセモノをキチンと見分ける力がなければ資料が資料としてうまく生きてくれないじゃん。だけど、権威的前中国的管理主義の東大や京大の漢籍分類目録を見てごらん。見てても本の姿がまったく目の前に浮かんでこないじゃないですか。あれじゃ、書誌って本来難しくて面倒なものなのに、それに輪をかけてわからないものをなおさらわからなくしちゃってしまっている。 「じゃ、お前やってみろ」と、誰かが言うだろう。はい…お楽しみに。ぼく、今、ベルギー、ルヴァン大学付属図書館、それから大東の図書館にある国書漢籍の分類目録を作っているところです。
図書館あちこち(六) ルヴァン・カトリック大学付属図書館(その一)
この大学図書館については、お話として(ベルギーという国柄のこともあるしさ!)とっても面白いこと、書きたいことが沢山あるから、二度に分けて…。 さてさて、第一幕のはじまり、はじまり。(…白黒で、第一次世界大戦の映像がフラッシュバックで流し出される、…音楽はぐっとくるマーラーの交響曲第五番、アダージョの最後の部分…そして、ナレーション) 「ブリュッセルから電車で一時間足らずのところにあるルヴァンという街、観光客はベルギーのショウベン小僧やブルージュに足を運ぶことはあっても、ほとんど、このルヴァンの街には立ち寄ることはない。立ち寄っても豪華な図書館が外から見られるだけで、対して訪れる場所もないからだ。しかし、ベルギー王国の第一次、第二次大戦の悲劇はここに大きな火蓋を切った。そして、そこには、書籍をめぐって世界中を注目させた事件が絡んでいたのだ…」(ドカーン、ドカーン、バン、バンという大砲と鉄砲の音、火の粉を浴びて燃え上がる街の映像)…こんなシナリオを続けるためには紙幅が足りなすぎるから止めましょう。でも、もし、時間があったら、こんな感じの記録映画を見ているような雰囲気を想像してみて下さい。 このルヴァンという街は、十七世紀初頭には、大学都市としての機能を既に持っていたらしい。一九一三年の図書の統計では二三万冊の蔵書というのだから、大英図書館のたった十分の一。それでも、ベルギーという国からすれば、やっぱり大学図書館としては、大きい蔵書を持っていたのだろう。そのルヴァンを、一九一四年、八月十九日、ドイツ軍は戦わずして占領してしまった。そして、ドイツ軍の将校は「この街を荒野に変えろ。街を破壊しつくすのだ」と叫びながら、火を放ったという。当然のことながら、二三万冊の蔵書を持つ、見事なバロック建築で飾られた図書館もゴーゴーと燃える業火に包まれて燃えてしまう。燃えてしまった貴重書…ヴェザリウスの『人体構造論』、十五世紀の写本集『コデックス・パルケンシス』、レニール・フォン・リュティヒの十二世紀の写本『オペラ』、一五一五から一五九一年の間に出版されたヴェルギリウスの作品集が全十六種類等々。世界中を探しても二度と見つからないこんなものたちが燃やされちゃったのだ。あーあ。で、このことを、ドイツ軍はさ、世界に向けて「我々は偉大な事業を行った。ドイツ文化を誇るため、ベルギーの大学都市を破壊したのだ」ってニュースを誇らしく報道しただって。(バカだね!)で、こんなこと聞いてさ、フランスとかイギリスなんか黙っているわけないじゃん。ロマン・ロランとか、H・G・ウエルズ、バーナード・ショーなんかはドイツを文化の破壊者なんて書き立てて攻撃するし、そうすると、誰もがさ、六四一年に起きたアラブ人によるアレキサンドリア図書館放火の話を思い出しちゃう。ってことで、ドイツは本当に悪者になってしまって、その中に敗戦…戦争の責任を負う裁判で、自分たちが焼いちゃったルヴァン大学の図書館にあったのと同じ質、量の本をドイツで用意して大学に弁償するようにってことに決まったらしいんだけど、何たって敗戦国だし、図書よりいろんなことで弁償しないといけないものもあるし、本って好きな人になら分かると思うけど、「はい、どうぞ」って、上げられないじゃない。特にさ、文庫本なんかじゃなく、貴重書なんだからね。ドイツの古本屋さんなんかが国からお金をもらっていい本を探したりするうちに、でも、時間ばっかり立っていく。貴重書なんて、簡単に見つかるようだったら貴重書じゃないもんね。で、フランス学士院は「ルヴァン国際支援運動」っていう組織を作って八万冊の図書を寄贈、イギリスのブリティッシュ・アカデミーや、アメリカからもそれぞれ三万冊くらいの寄贈があったらしい。あとは、個人の蔵書家ね。 日本もね、そして、もちろん、ここに登場するんですよ。昭和天皇がまだ皇太子だった頃、瓦礫の山になってしまったルヴァンを訪問されて、和書を寄贈されたんです。全く驚くべきコレクションをね。…約一万五千冊。そして、ルヴァンは日本にそのお礼をする。東京大学へ行ってごらん。デッカイ地球儀が置いてあるから。それが、ルヴァン大学からの返礼です。 とにかく…こうして各国、個人からの寄贈によって約四〇万冊の蔵書を手に入れたルヴァン大学…学問がようやく出来るって矢先…だけどね、哀しいことに…ドイツは第二次大戦が始まるとね、またしても、この大学図書館を空爆して粉々に破壊してしまったのです。…学者にとって有益だと思われた書籍はすべては燃え尽き、図書館の片隅に積み上げられていた、彼等には読むことさえ出来ない日本語の、しかも古書、…昭和天皇から贈られた和書だけが無傷で残っていたんだって。
図書館あちこち(七) ルヴァン・カトリック大学付属図書館(その二)
さて、ルヴァンの第二回。 第二次世界大戦でまたしても図書館を焼かれて灰侭に帰したルヴァン。ドイツの降伏によって平和が戻ると、ドイツからの賠償金をもとに、ドンドン本を買って、一九七一年の段階では既に百万冊の蔵書を誇るまでに増えたらしい。しかし、ね。「二度あることは三度ある」っていうのかな。百万冊まで本が増加したこの一九七一年、ルヴァン大学は三度目の破壊を受けたってベルギーの人たちは言うんだけど、ベルギー自身の問題であるワロン系とフラマン系っていう民族の争いに巻き込まれて二つに分裂してしまっちゃったのだ。 ワロンって言うのはフランス語系のひとたちのこと、そしてフラマンの方はオランダ語を話す人たちね。(このあたりの詳しい歴史については、自分で勉強して下さい)彼等は同じ国にいながらお互いのことが理解できず、互いにイガミあっているんです。だから、例えば、ブリュッセルに行ってね、フラマン系の人がやっているお店に入ったとするじゃない。そこで英語じゃなくて(オランダ語が出来ればそれが一番いいのかもしれないけど)フランス語を使うとさ、スッゴイ嫌な顔されて意地悪されたりするんだよね。ぼくなんか、ある時、フランス語で道を訊いたらさ、全く反対方向教えられちゃってとんだ目に遭わされちゃったりしたしね。で、こんな状態だから、首相だってワロン系とフラマン系って具合に二人づついたりするんだよ。変でしょ?…と、それはさておき、二つに分裂したルヴァン大学は図書館をどうしたかと言うとね。排架番号の奇数と偶数で二つに分けてしまったのです。(無茶苦茶だと思わない?)で、ルヴァンという街自体フラマン系の土地だからって言ってワロン族を追い出しちゃった。行き場を失なったフランス語系の人たちは、だから、荒野にルヴァン・ラ・ヌーヴ(「新しいルヴァン」という意味)という街を作り、大学を建てるより他なかったのです。 この新しく建てられた大学が「ルヴァン・カトリック大学」。で、戦争で焼け残った日本の和書のことだけど、フラマンの方は、こんな読めない本なんかいらねーってワロンと一緒にルヴァンから追い払ってしまって今、全部、カトリックの方に保管されている。でもね、皮肉なことってあるもんで…カトリックには語学系の学問はそんなになくて、日本語の講座はないのに、フラマンのルヴァンの方にはこれが八十年代に出来て、日本人の人も一人いらっしゃる。特に、日本文化講座の主査は、古典が専門。カトリック大学の方の調査中にぼくは、何度もこの人に食事に呼ばれて、何とかまたルヴァンの方に和書を戻せるように計ってくれないかって言われたけど、ぼくなんかにそんなことが出来るわけないじゃん。しかもさ、和書の価値が、ぼくの調査でわかっちゃったんだから…。 しかし、それにしてもこれ、このコレクション、こいつは、本当に宝だね。昭和天皇が命令を誰にだされてこの寄贈をされたのかわかんないけど、よく、ここまで満遍なく、ジャンルと本の種類とを選別して贈られたものだって感心するより他にない。 さすがに平安朝、鎌倉の写本はなかったけど、それでも先ず、五山版、古活字版、奈良絵本、八文字屋本、赤本、青本、黄表紙、元禄の江戸、大阪図それから伊勢暦なんか元禄から慶應まで欠損なく全部揃ってるんだから。これって天皇の御命による買い取りかなんかが行われた上になりたっているのかな…蔵書印をみると漆山又四郎、大野洒竹、和歌山藩校、東山御文庫って当時の個人蔵書家の錚々たるメンバーの名前や、由緒正しき文庫の名前がが出てくる出てくる。岩崎文庫を凝縮したらこんな風になりましたって感じ。しかし、このコレクションは一九一四年にベルギーに着いてから誰の目にも触れず、ただ、厄介もの扱いにされ、研究の対象とはされなかったのだ。日本では戦争で右往左往、空襲やなんかで本がドンドンなくなって行った時期をベルギーに送られたこれらの本たちは、こうして戦火を逃れていたんですね。だって、今じゃもう、高くて手が出ないような本がザワザワここにいるんだから。 …調査のために、ぼくは、結局一年間、このartificielに造られた荒野の街に住んだのだけど、車は盗まれる、壊される、毎日毎日学生たちは巨大なスピーカーを使って朝方までパーティを続ける…悲惨な目に遭いました。簡単なバカロレアさえ通れば、あとは学部なんて自分で適当に選んで何年も大学に残られるっていう単純なシステムではこんな風になっちゃうんだね。日本人がこの大学に足を踏み入れたのは、一九七一年以来、ぼくが三人目なんだって。…だって、和書を除けば、他に何もないんだもん。とにかく、ここの蔵書の目録を、解題を添えて、ぼくは今、作っている最中です。
図書館あちこち(八) ビブリオテーク・ナショナール(BN)、パリ
BNには、像の糞ほどの和書、中国書の資料が山積みされている。和書に関して言えば、奈良絵本とか五山版、古活字本、浄瑠璃本の類、そして、中国のものならペリオによって今世紀初頭に敦煌で発見され持ち去られた所謂敦煌本。これらの資料が必要なら、飛行機代も安くなったことだし、パリへの観光を兼ねてていうことで、誰もが、ここを訪れたいと考え、そして行くだろう。ある人は快く受け入れられるかも知れないし、そして、ぼくのようにあしらわれてしまうかもしれない。ご用心、ご用心。 人の悪口なんかぼくとしては本当は書きたくなんかないのです。でもね、パリで日本及び中国関係の仕事をするひとたちは異口同音にこれ以上の意地悪は生まれてこの方されたことがないって口を揃えて言う実態。ここにこんなことを書いたからって何かが変わるなんてこともないのかもしれないし、また、輪をかけて意地悪をされるかもしれないのだけど、クソッタレ!ぼくは、そんなことには負けないもんね。…とにかく、裏舞台をご披露いたしましょう。 先ず、BNに行きたいと思ったら(パスカルの自筆原稿を見たいという人はどうすればいいのかってのはぼくには分かりませんが、ここでは日本と中国の古籍を閲覧したいひとを対象にしています)、大学の先生であっても何でも、大学から、或いは研究機関からの紹介状があって、しかも、ここのビブリオテケール(司書)と事前に何を如何なる理由で見たいのかってことを知らせておかなければなりません。その手続きをしていないと、絶対に本は見られないから。で、お金も忘れないこと。国会図書館とは言え、ここでは年間の図書館使用料か、十回使いきりのチケットかを購入しなくちゃならないんです。まあ、ここまでは何とかうまく行くかもね。…で、この図書館の東洋部には日本人の女性の方が司書としていらっしゃるんですよ。当然、事前に連絡を取るとしたら、この人になっちゃうのかもしれないけど、ね。と、ぼくもここまでの手続きはケンブリッジ大学の研究員なんだから、スムースにやったのです。ところが、その先。ぼくなんか、林望の弟子ってことで、既にこの司書の方にチェックされていたらしいけど、開口一番。挨拶もなしに言われたこと。「ここは一応国会図書館ですから、資料を見せないということはできません。しかし、ケンブリッジ大学、そしてあなた方が企画している『欧州所在日本古典籍総目録』については、わたしは一切協力しません。だから、一日にあなたが見ることの出来る書籍は十タイトル。あとはノーコメントです」と。(ガーン。一日十タイトルなんて。全部で二千タイトル以上あるんだぜ。…ぼくはこの人がケンブリッジの仕事に全面協力を惜しまないっていうヨーロッパ図書館会議の時の協定書にサインした手紙だって持っている…)「しかし…それでは仕事になりませんよ」と言うと、「わたしの知ったことですか。手紙はコーニツキって奴が偽造したに決まっています」だって。…バカな。で、こんな時には口で争っても仕方がない。ぼくは早速目録を取りにかかるのだけど、この人、自分の事務室にぼくが見たい本は全部移動させちゃって、「今、その本はこちらで調査中ですから、それが終わるまでの何カ月かはお見せすることは出来ません」と、さ。そんなのあるかよなー、エーン、エーンと泣きながら、ぼくはこれまでずっと見たかった敦煌本を出してもらって(中国の詩を専門にしているフランス人の司書の人は優しいよ)調査していると、ぼくの背中を叩くものがある…書庫から閲覧室へ本を運んでくる司書でもなんでもないおばさん…「日本人のひと帰ったし、部長もどっかへ行っちゃったから。内緒でね…隅の方に行ってやんなさいよ」両手には抱えきれない程の本を持っている。…閲覧者を監督している中国の詩を専門にしている女の人を見ると、ぼくに目配せをしてくれる…ボン。メルシィ、シェシェ、グラーツィェ、スパイシーボ。 「あの人ね、十年以上ここにいて、何かやってるんだけど、書誌なんて全くやったことない人だし、古典なんて、とってもとっても」と、いう話。「あなたみたいな人がくると、自分の仕事がとられちゃうんじゃないかって思って、悪い噂をあることないこと振りまいてあるくのよ…」実際、この後、ぼくはこの人によってばらまかれた悪い噂にとりまかれあったことも見たこともない人たちからいろんなことを言われていたらしかった。そして、それは日本にまで飛び火している…そんな人たちに逢って話すと、必ず言う。「まさか、ヤマグチさん、BNで仕事をしていた話に聞くヤマグチさんとは別のひとなのかな?」 三木清は、結局、これに似た出所のわからない噂によって京大の職を得ることが出来ず、獄中で死ぬことになった。そして、横山重は慶應大の職を追われ『書物捜索』という仕事によって自分を守ったのだ。
図書館あちこち(九) スウェーデン、極東図書館
港があるせいかな、ストックホルムは長崎に似てて、ぼくは、故郷に帰ったような気分だった。久しぶりにケンブリッジから合流したピーター・コーニツキと逢えたし、ぼくは、BNとそこから流出した噂とのただ中から解放されたってこともあったのかもしれない。そして、ぼくらがストックホルムに着いたのは、クリスマスの十日前。街中のすべての窓には、三角形をした木枠の両辺にろうそくをあしらったランプが光り、広場はスケートを楽しむ老若男女でわき返っていた。 ぼくらは二人でアパートを借り、朝食を作って、バスに乗り、手分けしてストックホルム現代美術館の隣に建つ(昔の海兵学校の建物を利用したもの)極東図書館の蔵書の調査を行った。和書に関して言えば、そのほとんどは、大抵、どこかで容易にお目にかかることが出来るようなものばかりで特筆すべきようなものはない。床本がグチャグチャになって段ボール箱に押し込んであって、ピーターは「床本ってあんまりよくわからへんやん。きたないし、さわりとうないし…」とか言うもんだから、ぼくは、そっちの担当ってことになる。漢籍も、そうだね、清朝後期あたりに出版された本が整理されてあるんだけど、ここに取り上げて書くようなものは、ない。ただ、この漢籍。おもしろくはないと言っても、かの有名なバーナード・カールグレン博士が亡くなる寸前まで手許に置いてらっしゃった書籍なんだよね。ページをめくって行くと、博士の手になる鉛筆の書き入れが、ときどき見つかる。…カールグレンって言っても知らない人も多いだろうけどさ。と、いうわけで、…カールグレン。 早い話が、中国古代、中世の音韻形態がどのようなものであったかを、ローマナイズされたIPA(国際表音文字記号)で、世界ではじめて手にとる形に見せてくれたスウェーデンの学者なんです。論文の名前は「Etude sur la phonologie chinoise」(一九一五年、ストックホルム、gothenburg刊)。中国って漢字ばっかりの国でしょ?それまではね、「反切」と言われるシステムを使って漢字の発音を漢字を使って、ずっと、示していたんですよ。例えば、「東」という漢字はどう発音するかというと、「徳紅反」と書いてある。中国語ってのは、単純に<声母+韻母>という組み合わせから出来ているから、この「東」の音を知るには、まずこの反切の「徳」から声母を導き出す。現代中国語だったら「de」だよね。で、声母が欲しいんだからこの「de」の「d」が、「東」の声母。で、次に韻母。韻母は「紅」から探してくる。現代中国語でだと「hong」。だから韻母の方は「ong」。で、互いから導き出された声母と韻母を足すと、<d+ong=dong>ってなって「東」の音が抽出されるという訳。で、こんな反切で漢字の音を示した『広韻』とか『切韻』とかいう中国の七世紀ころに作られた辞書があるんだけど、カールグレン博士がIPAを使って研究の成果を発表する迄は、中国人も日本人もひたすら漢字を使ってこんな七面倒くさい作業をやっていたもんだから分かったような分からないことになっていたのです。特にね、韻母には、「介音」とか「主母音」とかいうものがあって、漢字で漢字を扱ってみてもうまくわかんないんだよね。と、いうことで、勿論、博士の研究は、フランス人のマスペロとか、日本の有坂秀世なんていう研究者から補正され訂正されたりはするけど、まあ、何と言ってもこの博士の研究なくしては、中国音韻学は語れないものなんだよ。で、ついでだけど、博士の研究のサブタイトルからも分かる通り、これによって、万葉集とか、日本書紀なんて漢字で書かれた日本の古代の文献の音韻形態もいろんな意味で明るくなった。 ところで、ぼくは、東洋文庫で林望師匠のもと、岩崎文庫の解題(『岩崎文庫貴重書解題1』)を作るために書誌に精を出していたんだけど、同時に当時日本研究室長だった故亀井孝先生にお弟子入りを許されて、言語のことにも深く沈潜していたんで、(勿論、音韻がわからなくては文献学なんて出来ないしさ)、カールグレンの旧蔵書なんて聞くと、やっぱりね、胸がワクワクするんだよね。と、いうこともあって、極東図書館の東洋部長フレデリクソンさんと一緒にカールグレンが再構成した中国中世の音韻をコンピューターに入力して、如何なる理由によって誰がどうやって博士の研究を訂正したかっていうことが一目瞭然でわかるようにして、既にもう四年前からこれはインターネット上で公開されています。 でも、それにしても、この極東図書館。ぼくらはずっと前から連絡を入れて何時開館しているのかって問い合わせしてたんだけど、ほとんど開いていることってないんだよね。「春は光の中で戯れるために二カ月、夏はバカンスでどっか行っちゃうから三ヶ月、秋は冬の準備のために二カ月、冬は十一から三月まで冬眠のため、いづれも休館」。信じられる?これ、フレデリクソンの言葉だよ。
図書館あちこち(十) 最終回 ミッション・エトランジェール(外国布教教会)付属図書館 「ミッション・エトランジェールには古い本が沢山あるよ」という話を聞いたのは、ルヴァン・ラ・ヌーヴにいた時だった。古い方のルヴァンで、六〇年代をずっと学生で過ごしたという、現在韓国のある大学で哲学を教授する南先生がサヴァチカルでルヴァン・カトリック大学に滞在されていて、ぼくらは、互いにルヴァン・ラ・ヌーヴの小さな街の中で煙草を探し回っていて知り合ったのだ。雪が降りしきる日曜日の朝、すべての店はシャッターを締め、道には猫の子一匹いなかった。…この街に着いて先生は二日目、ぼくは三日目…当たり障りのない挨拶から始まったぼくらの会話は、夜中、ビールを飲んで三箱目の煙草がなくなるころには、三〇年来知っている親子のように弾んでいた。 「パリに上った時、一度、ミッション・エトランジェールを訪ねたことがあってね、そこで、わたしは見たんだ」と、プロフェッサー・ナムは言った。「段ボール箱に山のように日本や韓国や中国の古い本が入っているのをさ」 …その話から一年後、プロフェッサー・ナムは韓国に帰り、ぼくは、ミッション・エトランジェールの書庫で仕事を始めていた。氏が言っていように古い中国、韓国、日本の古書はそこにあった。…段ボールにではなく、書架にきちんと並べられて。 ぼくの中で膨らんでいた、キリシタン版が見つかったりするんじゃないか、という期待は裏切られたけれども、しかし、ぼくは、ここで出会った司書のアニー・サブライロル女史によって沢山のチャンスを与えられることになった。パリ高等研究院大学院言語学科博士過程への入学、ローマ国会図書館、並びにローマ法王庁付属図書館への調査への便宜等々…その他、有形無形、陰日向。 ぼくは、大学が休みになればパリに戻る。「戻る」と、いうのは、パリに家があるからだ。日本にいては、フランスののメディアに出たりとか、その他、いろんな出来ないこともたくさんある。また肝心の『欧州所在日本古典籍総目録』のプロジェクトも、それを推進するための経済的困難、林御師匠の多忙、ピーターの個人的理由、ぼくの帰国等々の理由で遅々として進まない。それから、さらにぼく個人のことで言えば、前に書いたベルギー、ルヴァン・カトリック大学所蔵国書目録の編纂、フランスで、あるひとと内緒で始めた、ある文庫の解題目録作成のための調査もある。スウェーデンのフレデリクソン博士とは、中国の中世音韻の体系を古代のそれに引き比べて音の変遷をもっともっと具体的にみんなに分かるようにコンピューター処理しようよ、との話(音が出るようにしようとか、映像を使ってみようとか…)もある。とにかく、やりたいことばかりが続々なのだ。 と、こんなに楽しく仕事が出来るのも、ヨーロッパ中の図書館をあちこち歩かせくれた林の師匠、ケンブリッジ大学、そして、そこでの出会った人たちのお陰だと、この連載を書きながらつくづく思う。 図書館の扉を叩いて歩くことは、非常にきつい。時には、いろんな理由をつけられて拒否されることだってある。毎日、毎日、目録をとってもとっても、本は山のようにぼくの目の前に高く聳えたっているし、ここが終われば、明日はまた別のところへとカタツムリのように移動して行かなければならない。そして自分の本でないんだから、それなりの配慮は当然いるし、目録をとって回っている以上、おもしろいものがあるからと言って、何日も何週間もひとつの本だけにかかり切りになってはいられない。目録をとるっていうのは、簡単にいうと、戸籍調べをするようなもんなんだよね。とりあえず、外見からだけ見て(当然内面をも考慮するんだよ)、この本がいつ、どこで、だれによって作られたものかという情報を調査し、的確に簡潔に分かり易い方法で人に伝えなきゃいけない。だから、本を手にとって「こんにちは」というと、なかなか「彼」の内面にまで立ち入って悩みを聞いてあげたりっていう暇もなく「さようなら、元気でね」だもんね。…なんだか寂しい気もするけど、だけど、勇気を出して、明るく扉をノックして見れば、そこにはきっと新しい世界が待っている。 ここでは、紹介できなかった図書館もまだ、まだ沢山ある。楽しかったことも、哀しかったことも含めてね。だけど、それは、別の機会を得て書くことにしよう。