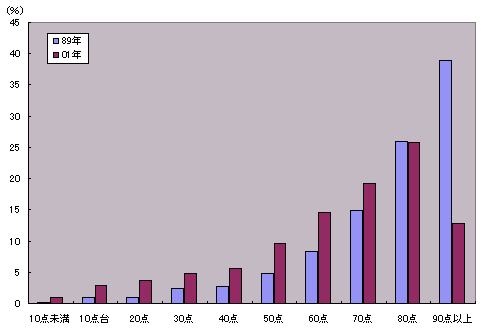
法学部 法律学科3年
平林 圭一
近年、子供の学力が低下していると言われている。事の発端は、文系学部を対象とした京都大学経済研究所教授の西村和雄氏と慶應義塾大学経済学部教授の戸瀬信之氏による1998年の数学学力調査の結果である。彼らによれば、
1.私大のトップ校の経済学部でも分数・小数などの算数レベルも危うい学生がいる。
2.私立上位校でも数学未受験の学生の数学力は中学2年生程度である。
3.国立大の最難関校の学生でも入試で数学を経験していない学生の多くは中学の数学もできない。
とされている。そんな中、完全学校週5日制と「ゆとり教育」の完成形とも呼べる新しい学習指導要領が実施され、学力低下を憂慮する声はさらに高まっている。
しかし、実際に学力は低下しているのだろうか。使わないために忘れているだけで少し勉強すれば当然のように解けるようになるのではないか。それではいけないのか。また、数学未受験の学生の数学力が中学2年生程度というのは今に始まったことなのだろうか。西村氏、戸瀬氏の調査は1998年のものに限られ、それ以前との比較はなされていない。にもかかわらず学力が低下しているという以上、そこには何らかの根拠が存在しているはずである。そもそも、学力とは何なのか。問題が解けなければ学力が低いことになるのだろうか。そういったことを考えていきたい。
そもそも、「学力」とは何なのか。「学力」という言葉を辞書で引くと、「学校などにおける系統的な教育を通じて獲得した能力。教科内容を正しく理解し、それを知識として身につけ、その知識を応用して新しいものを創造する力。」(大辞林 第二版より)と書いてある。一つ目の意味は、獲得できる能力が教育内容に依存することから、テストでどの位の点が取れるかなど、つまり、「成果」としての学力であり、二つ目は、学習することそのもの、つまり、「学ぶ力」としての学力である。では、学校などにおける系統的な教育を通じていないものは学力ではないのか。学力が「学ぶ力」であるならば、習い事やスポーツを学ぶことも学力につながるのではないか。結論から言えば、学力には含まれない。なぜなら、言葉の定義は、個人が定めるものではなく、世間一般が定めるものであるからである。例えば、日本中の人がある言葉を一定の意味で使用すれば、それは用語として認知され辞書にも載るが、もし、使わなくなれば、辞書からは消えるのである。おそらく、サッカーがうまい事やピアノがうまい事を学力が高いと思っている人は殆どいないだろう。つまり、将来、「スポーツ=学力」とされることがないこともないが、現在、「学ぶ力」とは学問に限定されることになる。では、学問とは何か。辞書によれば、「1.一定の原理によって説明し体系化した知識と、理論的に構成された研究方法などの全体をいう語。2.勉強をすること。知識を得るために学ぶこと。また、それによって得た知識。」である。つまり、学問の範囲は国語や数学などに限られるものではなく、知識として蓄えられるものであれば良いわけである。例えば、コンピューターについての知識を学ぶことも学問であり、また、スポーツなどを技能としてではなく、トレーニング理論や指導法など、知識として学ぶことも学問と言える。
では、知能偏差値のような先天的能力は学力と呼べるのか。例外はあるにしろ、知能偏差値が高ければ学力テストなどにおいて、他よりも高い成績を修めるはずである。しかし、前述の通り、学力とは「系統的な教育を通じて獲得した能力」もしくは、「学ぶ力」である以上、知能偏差値の高低は含まれないことになる。また、教育心理学には[学力偏差値−知能偏差値=成就値]という考え方があり、成就値がゼロであれば、その子供は知的能力に応じた学習成果を上げていることになり、マイナスであれば、何らかの要因により学習成果が上がっていないことになる。ということは、知能偏差値が高くてもそれに応じた成果が上がらなければ学力は低いということになり、この事からも知能偏差値は学力に含まれないと言える。
以上のことから考えると、「学力」とは後天的に身につけた力で、1.学校のテストなどでどの位の点数が取れるかという「成果としての学力」と、2.学問を「学ぶ力としての学力」の二つを合わせた言葉であると考えられる。
第一節では学力とは何かをみてきたが、それでは、現在、盛んに叫ばれている学力の低下とは何が低下しているのか。例えば、国語力について言えば、かつて使われていた熟語や漢字であっても、現在はまったく使われず、辞書にすら載っていないものもある。つまり、言葉の使い方などは時代とともに変わっていくものであり、それを単純に比較して学力が低下していると言うことは出来ない。成果としての学力を現在とある時点で比較するのであれば、普遍的なもの、つまり、両時点において学習指導要領に記載されているもので比較しなければならず、また、同一の問題で同時期に同様の形式で比較しなければ意味がないのである。しかし、成果としての学力とは違い、学ぶ力としての学力は普遍的なものである。対象がなんであれ、学ぶ力の内容は変化しないからである。そして、成果としての学力よりも学ぶ力としての学力が低下することこそ憂慮すべきことである。なぜなら、成果とは一定の事柄を対象とした一時のものであり、たとえ急落したとしても、それには、外部的、もしくは内部的な影響も考えられ、回復する可能性もあるが、学ぶ力は一朝一夕で身につくものではなく、また、蓄積されていくものであり、成果は上がっていても学ぶ力が低下していれば、対象が難しくなるにつれ急激に成果が上がらなくなる可能性があるのである。
つまり、学力の低下は、学習指導要領の範囲内で過去よりも成果が劣っている場合、学ぶ力が低下している場合、もしくは、それら両方が低下している場合に起こるのである。
ここからは、小学5年生と中学2年生を対象とした調査結果を検討していく。この調査結果は、1989年(以下89年)に大阪大学のグループが実施した「学力・生活総合実態調査」の結果を、苅谷氏らが2001年(以下01年)に同様の問題と採点基準によって再調査した結果を比較したものであり、1992年の学習指導要領改訂に伴い削除された問題については含まれていない。(注1)
この学力調査は国語と数学(小学校では算数)を対象に行われ、理科や社会、英語に関しては調査の対象になっていない。理由は分からないが、しかし、これらの科目は過去の調査結果があったとしても比較対象としては相応しくないものであろう。なぜなら、国語ならば接続詞や指示語の問題など使い方が分かれば文章の中でも応用が効くし、数学は数式の応用そのものであるが、小中学校の理科は暗記によるものが多く、社会は暗記科目であるため、たとえ点数が下がっていたとしても覚える以外に方法がないのである。英語については、小学生では学習指導要領には記載されていないし、中学生であっても、近年との比較であれば参考になるが、89年と01年では英語教育に対する捉え方がまるで違うのである。例えば、英会話学校に通っている子供の数は89年と01年ではまったく違うだろう。つまり、数字が上がっていようと下がっていようと、外部的要因が違いすぎるため、比較にならないのである。これらのことから、学力の比較は国語と数学(算数)に絞ることが望ましいと考えられる。
まず、小学生の学力の変化を見ていく。89年では、国語の平均点が78.9点、算数の平均点が80.6点だったのに対し、01年は国語が70.9点、算数が68.3点と、国語では8.0点、算数では12.3点低下している。算数の得点を10点刻みのグループに分け、その分布をグラフ化する(表1)と89年のグラフは右肩上がりのカーブを示しており、最も人数が多いのが90点以上で38.9%、80点台が25.9%と6割以上が80点以上だったのに対し、01年のグラフは最も多いのが80点台の25.8%で、90点以上は12.8%と激減している。通塾との関係を見ていくと、表2を見て分かるとおり、どちらの時点においても通塾者の方が非通塾者よりも平均点が高くなっている。これは、学校に通う以外に塾に通っているのであるから当然ではある。しかし、通塾者、非通塾者とも12年間で大きく点数を下げている。また、通塾者であっても、01年の通塾者は89年の非通塾者よりも平均点が低いのである。つまり、塾に通っているからといって安心できるわけではなく、塾に通っていたとしても、89年時に塾に通っていなかった者よりも点数が悪い場合がある、と言うよりむしろ、悪い場合の方が多いのである。ちなみに、89年の通塾率は29.2%、01年は29.4%で通塾率の有意差は見られない。
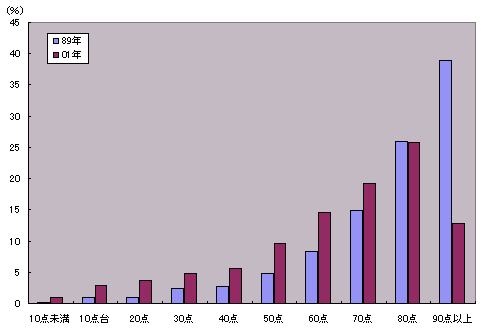
| 89年 | 01年 | 89年と01年の差 | ||||||
| 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | |
| 国語 | 80.9 | 78.0 | -2.9 | 75.9 | 69.6 | -6.3 | -5.0 | -8.4 |
| 算数 | 84.6 | 78.9 | -5.7 | 73.0 | 67.5 | -5.5 | -11.6 | -11.4 |
教科別に見ると、どの項目が低下しているのか。国語の得点から見ていく。
| 長文読解 | 漢字 | 文法 | 文章構成 | |||||
| 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | |
| 平均点 | 65.79 | 56.62 | 82.13 | 78.90 | 83.06 | 74.67 | 37.38 | 32.43 |
表3を見て分かるとおり、すべての項目において点数が低下している。中でも長文読解と文法の低下幅が大きい。さらに細かく見ると、指示語の設問や主語・述語の設問の正答率が15〜60%と89年時でも低かった(正答率30〜70%)ものがさらに低下している。
続いては、算数の得点を見ていく。表4は算数の項目別の得点を通塾と非通塾との関係で表したものである。
| 89年 | 01年 | 89年と01年の差 | ||||||
| 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | |
| 数と計算(概念) | 85.1 | 75.9 | -9.2 | 80.0 | 74.4 | -5.6 | -5.1 | -1.5 |
| 数と計算(計算) | 89.5 | 81.0 | -8.5 | 84.5 | 76.5 | -8.0 | -5.0 | -4.5 |
| 量と測定 | 77.6 | 58.4 | -19.2 | 69.3 | 55.5 | -13.8 | -8.3 | -2.9 |
| 図形 | 82.5 | 68.5 | -14.0 | 77.8 | 64.3 | -13.5 | -4.7 | -4.2 |
| 数量関係 | 85.3 | 65.4 | -19.9 | 79.5 | 62.0 | -17.5 | -5.8 | -3.4 |
これをみると、国語と同様にすべての項目において点数が低下していることが分かる。また、算数全体で見たときと同様に89年、01年ともにすべての項目で通塾者が非通塾者を上回っている。しかし、この表3で興味深い点は通塾と非通塾の差である。89年は最大で8.3点の差があったが、01年では最大でも4.5点に縮まっており、すべての項目でその差は縮まっている。つまり、塾に通っていない子供よりも、塾に通っている子供の成績が低下しているのである。言い換えれば、塾に通うことで得られる効果が89年時よりも低下しているということである。
中学生の学力の変化を見ていく。89年では、国語の平均点が71.4点、数学の平均点が69.6点だったのに対し、01年は国語が67.0点、数学が63.9点と、国語では4.4点、数学では5.7点と、小学生ほどではないがやはり低下している。小学生のときと同様に数学の得点を10点刻みのグループに分け、その分布をグラフ化する(表5)と89年では、綺麗な右肩上がりとはいかないものの、90点以上のものの割合も多いことが分かる。しかし01年では、もっとも多いのが80点台で、90点台、70点台という89年時の平均点を上回っている者の割合が減り、代わりに40点未満の割合が増加している。折れ線のグラフは、最近言われる「子供の学力低下は全般的に起こっているというより、出来る子供と出来ない子供の格差が拡大し、ふたコブ化が進んでいる」ということを表したものである。通塾との関係を見ていくと、表6のとおり、通塾者の方が非通塾者よりも平均点が高い。これは、小学生のときと同様であるが、しかし、その差は大きく拡大している。小学生のときと違う点は通塾者の得点はほとんど変わっていない点である。確かに、国語、数学共に下げてはいるが、これは有意差とは呼べないものである。その代わり、非通塾者の得点は大きく下がっており、01年の子供は学習内容が難しくなるにつれて、学校の授業だけでは内容を理解できなくなっていることを表している。通塾率は89年が54.4%、01年が50.7%で、むしろ低下していると言える。
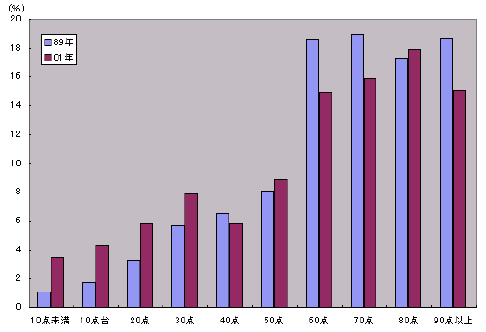
| 89年 | 01年 | 89年と01年の差 | ||||||
| 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | 差 | 通塾 | 非通塾 | |
| 国語 | 74.5 | 68.3 | -6.2 | 71.9 | 63.2 | -8.7 | -2.6 | -5.1 |
| 数学 | 75.8 | 62.5 | -13.3 | 74.5 | 54.5 | -20.0 | -1.3 | -8.0 |
| 長文読解 | 漢字 | 文法 | 文章構成 | 語彙 | ||||||
| 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | 89年 | 01年 | |
| 平均点 | 61.39 | 56.69 | 68.74 | 66.59 | 84.46 | 76.15 | 48.59 | 50.36 | 75.16 | 72.02 |
表7は国語の項目別の比較であるが、文法が8点以上下がっている点を除けばそれほど大きな差はないように思われ、文章構成にいたってはわずかではあるが増加している。このことは数学にも言えることで、項目別に見ても、小学生とは違い、大きく低下しているような項目は見受けられない。やはり、問題となるのは表6で示した通塾者と非通塾者の学力差の拡大ということになる。小学校時よりも通塾者と非通塾者の学力がひらいているということだけであれば、通塾率が、進学により20%台から50%台に増加したことによるものであると考えられるが、差が拡大していることは、「成果を上げる」ということに関しては学校教育の質が低下していると言わざるを得ない。
では、成果としての学力は低下しているのかと言えば、一概にそうとも言えない。なぜならば、これらの数字がそのまま日本全体の学力を表しているとは言い切れないし、第一章でも触れたが、成果としての学力は内的、もしくは外的要因に影響されるものである。つまり、01年が何らかの理由によって低いだけと言う可能性もあり得るのである。調査対象が小学5年生と中学2年生に限られているという点もある。おそらく89年の調査結果がその2学年しかなかったためであろうし、89年時は中学2年生であれば、中学受験の1年後、高校受験の1年前ということで比較的平常時の学力が計れるということで採用したのであろうが、子供の学力を調査するのであれば、全学年を調査することが必要であろう。また、この調査結果はすべてが公開されているわけではなく、調査グループが評価した内容のみが公開されている。つまり、受け取る側にとってデータが完全ではないため議論の余地が少ないのである。加えて、対象となっている89年であるが、この年にも問題がある。西村氏と戸瀬氏が大学生の学力について報告したのは1998年である。つまり、かれらにより、数学力が中学2年生レベルしかないと言われたのは、89年の小学5年生ということになる。確かに、苅谷氏らは89年時よりも01年の学力が低下していると言っているだけであり、89年の学力が高いと言っているわけではない。また、1989年に学習指導要領が改訂された際に導入された「新しい学力観」が彼らの学力を低下させたのかもしれない。しかし、仮にそうであってもこの調査だけで学力が低下していると断言することは出来ない。例えば、文部科学省が実施した平成13年度教育課程実施状況調査では解釈の仕方によっては上がっていると見ることも出来るのである。また、IEA(国際教育到達度評価学会)が行っている「国際数学・理科教育調査」では、常に上位の成績を収めている。だが、この二つの調査で学力低下はないということも出来ない。文部科学省の調査は同一の学習指導要領のもとで調査されたものであり、また、設定通過率というもので評価しているのであるが、この設定通過率の基準が明らかにされていない。IEAの調査についても、教育についての考え方が違う国家間での比較がどれほど信頼できるものなのかという問題がある。つまり、学力の低下を計るためには全国規模で継続的に調査を行い、比較検討する必要がある。
学ぶ力を比較することは難しい。そもそも、数字で現れるものではないし、それ自体を比較することは不可能と言っていい。それでは、どうやって変化を見るのか。それには、学ぶ力を身につける要因について考えればいいのではないか。学ぶ力を得る機会が減少していれば、当然、学ぶ力も減少するはずである。学ぶ力とはどうやって得るものなのか。それは、学ぶことによって得られるものである。すなわち、学ぶ時間が減少すれば、学ぶ力は減少するのである。しかし、ただ学ぶだけで増加するものではない。ここでの「学ぶ」とは、自分で考えることであり、自分で答えを出すことである。もちろん、答えが間違っている可能性もある。もし、答えが間違っていれば、今度は何故間違ったのかを考える。どうしても分からなければ、そこで初めて人に聞く。そういったことを繰り返すことが「学ぶ」ということである。
苅谷氏らの「学力・生活総合実態調査 (注4)」によれば01年の子供は89年時よりも学校以外で学習する時間が減少している。家で勉強する時間は小学生では53.6分から40.7分、中学生では43.7分から29.1分に減少している。また、小学生ではあまり変化は無いが、中学生では、学校の宿題、予習、復習をしないものの割合が10〜20%以上も増加している。文部科学省が学力低下はないという根拠にしてきたIEAの調査でも、日本の学力は世界トップではあるが、その学習時間は世界最低ランクである。ということは、日本人は自宅で学習する時間はほとんどないといっていい。2002年には学習指導要領が施行され、完全学校週5日制が採用された。チャイルド・リサーチ・ネットの調べでは週5日制によって休みになった土曜日に「自分で勉強する時間が増えた」と答えたのは43.2%である。このこと自体は学ぶ力をつけるためには良いことである。しかし、それ以外の57.8%は学校に行かなくなった時間分だけ学習時間が減っているのである。また、週末が連休になったことで「月曜日に学校に行くのがつらい」と答えているのが50。7%、「月曜日は、なんとなくだるい」と答えているのが56.4%と、月曜日の学習に悪影響を及ぼしている可能性もある。
なぜ、学習時間が減っているのか。どの調査結果でも、かつてと比べてテレビを見る時間やTVゲームをする時間は増加している。いまやテレビは一家に一台ではなく一部屋に一台だろう。つまり、他にも出来ることがたくさんあるのである。おそらく、調べ物をしようとしてホームページを見ていたら、知らないうちにネットサーフィンになっていたり、論文を書こうとしてパソコンを起動したら別のことをしていたりするのと同様であろう。勉強をする気がないのではなく「明日で良い」と思っているのである。また、学習意欲そのものの低下も関係している。これについてはいくつかの理由が考えられる。まず、「少子化」である。一昔前までは受験戦争などと言われ受験は狭き門であった。しかし、少子化が進むにつれて競争倍率が低下し、今では廃校になるところもある。倍率が低下すれば、競争意識も低下する。つまり、受験に対するモチベーションが低下するのである。モチベーションが下がれば学習時間が減少するのは当然のことであろう。次に、「関心の低下」である。日本は理科、数学(算数)が好きな生徒の割合は、小学生までならば国際平均、もしくはやや低い程度なのだが、中学生になると平均を大きく下回ってしまう。楽しいかという質問でも同様である。興味が無いことを率先して勉強する子供はほとんどいないであろう。最後はバブルの崩壊、つまり、不景気である。OECD(経済協力開発機構)の調査によれば、経済力と学力とは密接な関係があるという結果がでている。また、他の調査でも文化的階層と学力の関係が言われている。これらは同一国内の中における階層と学力の関係を言ったものであるが、もともとは高かった経済力が急激に落ちれば、同様のことが言えるのではないか。以前の日本は「学歴社会」と言われ、高学歴を修めればいい仕事に就け、いい暮らしが出来ると信じられてきた。しかし、経済の崩壊により高学歴でも職に就けない、リストラされるという現状を目の当たりにし、努力しても無駄ではないかとい考えが生まれ、学習意欲が低下したのである。そして、苅谷氏らの調査に使われた1989年というのは学習指導要領の改訂とともにバブル景気の絶頂とも重なるのである。
これらのように、学習時間が減少し、学ぶ力が低下していると言える要因はある。確かに、学ぶ力は学ぶことによって得られ、学習時間が減少すれば結果として学ぶ力が低下するという前提ではあるが、学習時間の減少は事実であり、このことが子供の学力の変化に影響を及ぼしているのもまた事実である。
学力の低下を防ぐためにはどうすればいいのか。もちろん、学力は低下していないと考える人もいるだろう。しかし、仮に学力が低下していないとしても、これから低下しないと断定することは出来ないはずである。それではどうすればよいのか。文部科学省は従来の知育偏重の詰め込み型の教育方針を改め、個性を生かす教育に重点を置いた「ゆとり教育」を行ってきた。そして、その完成形とも呼べるものが現在の学習指導要領であり、「完全学校週5日制」である。しかし、週5日制にすることが本当にゆとりを生むのだろうか。おそらく、ゆとりを生むことはないだろう。私立の学校では学習指導要領に縛られることはなく、公立の学校では扱えないものも扱うことが出来る。つまり、公立校出身者と私立校出身者の進路が交わった場合、その知識には大きな差が出来ることになる。ということは、学校で扱わないものに関しては塾で学ぶか、自力で学習することになる。それはそれで学ぶ力になるだろうが、目標であったゆとりを生むとは考えにくい。「ゆとり」とは時間が生むものではなく、自信によって生まれるものである。出来るという自信があれば多少時間がなくてもそれほど焦ることはないだろうが、自信がなければどんなに時間があってもゆとりを持つことは難しい。ゆとりを生まない「ゆとり教育」は、子供の学習範囲を無駄に制限しているだけである。重要なのは興味を持たせることとやる気を引き出すことである。
日本の教科書は他の先進国と比較すると圧倒的に薄い。厚ければいいというものでもないが、例題と問しかないような教科書に興味を持つだろうか。多少厚くなっても、子供が興味を持つような内容も載せていけば学習意欲も増すのではないか。英語であれば簡単である。もう行っているのかも知れないが、折角日本人が海外で活躍しているのだから、内容もそういったものにすればいい。多少難しくても読めるはずである。著名な文学者でも医学書は理解できないだろうが、医者は目を通すだけでもある程度理解できるはずである。なぜなら、内容がある程度分かっているからである。つまり、文章が身近な内容であれば、きちんとした訳は出来なくても理解できる。そうやって、文章に興味を持ったらあと、文法などの細かい部分を教えればいいのである。
子供の興味とやる気を増す上で重要なことがもう一つある。それは、教師との信頼関係である。好きな教師だからその科目の勉強をするというのはよくあるが、嫌いな教師の科目であれば、相当その科目が好きでない限りは必死に勉強することはないだろう。当然、学校にいる子供は一人ではないので、全員の信頼を得るというのは至難の業だろう。おそらく、学力の低下を防ぐよりも難しいに違いない。けれども、教師が子供の信頼を得ることが出来れば、学習指導要領がどういったものであろうと学力の低下は起こらないであろう。学力の低下を防ぐ最良の方法は国の適切な方針の下、教師が子供との信頼関係を築くことである。
私は、学力低下は起こっていると考えている。それも、成果と学ぶ力の両面からである。理由は二つある。一つ目は、先日、中学生レベルの問題を解く機会があったのだが、まったく出来なかったからである。昔の大学生がどの程度数学が出来たのかは分からないが、因数分解と言われて全くどうすればいいのか分からなかった。それでも、平均点を上回っていたのだから、文系の大学生の数学力は相当なものである。もう一つは、今回の論文を書くにあたって調べた結果である。「低下している」というよりは、むしろ「低下していないはずがない」というのが正直なところである。今回の論文では、低下していることを証明するには至らなかったが、文部科学省が今後も学力調査を実施することを明言しているため、いつかは証明される日が来るであろう。
この論文を書いている際、自分の時を思い出しながら書いていたのだが、一つ思ったことがある。因数分解が出来なかったと書いたが、元々数学が苦手だったわけではなく、高校1年まではむしろ得意科目だった。確か高校1年の時だったと思うが、テストで97点をとったことがあった。解答を間違えたならば納得いくのだが、途中式から答えに至るまで、どう見ても模範解答そのものであるにも関わらず、サンカクで−3点だったのである。おそらく、何らかの理由があったのだろう。何が言いたいのかといえば、いい点数を取れば誰でも自信になるということだ。にもかかわらず、テストの採点が厳しすぎる気がするのである。「本当はバツを付けたいがサンカク」なら分かるが、「ほとんどマルだけどサンカク」は子供のやる気を失わせはしないか。間違ったまま覚えさせたくないのであればマルにして注釈でも付ければいい。評定が変わらない程度であれば何の問題もないだろう。(ちなみに、サンカクで100点を逃したことが理由ではないが、高校2年の時は0点をとった。)
論文の最後に、子供との信頼関係について書いたが、教師の側から見れば家庭との関係や子供の気質の変化のこともあるだろう。しかし、それで諦めてしまえば、ただの職務放棄である。最近は、子供の学習意欲だけではなく、教師の指導意欲も低下しているのではないか。学力低下を防ぐためには教師の自信を回復させることも必要なのではないかと思う。
| ・子供の学力とは何か | 水野重史 | 岩波書店 |
| ・学力とは何か | 中内俊夫 | 岩波新書 |
| ・学力問題と教育政策 | 日本教育政策学会 | 日本教育政策学会 |
| ・学力があぶない | 大野晋・上野健爾 | 岩波新書 |
| ・ゆとりを奪った「ゆとり教育」 | 西村和雄 | 日本経済新聞社 |
| ・分数が出来ない小学生 | 岡部恒治 戸瀬信之 西村和雄 |
東洋経済新聞社 |
| ・「学力低下」の実態 | 苅谷剛彦 志水宏吉 清水睦美 諸田裕子 |
岩波ブックレット |
| ・「学び」から逃走する子供たち | 佐藤学 | 岩波ブックレット |
| ・学力低下と新指導要領 | 西村和雄 | 岩波ブックレット |
| ・文部科学省ホームページ | http://www.mext.go.jp |
| ・チャイルド・リサーチ・ネット | http://www.crn.or.jp |
| ・アサヒ・コム | http://www.asahi.com |
| ・NIKKEI NET | http://www.nikkei.co.jp |
| ・毎日新聞 | http://www.mainichi.co.jp |
| ・IEA | http://www.iea.nl |
| ・OECD東京センター | http://www.oecdtokyo.org |