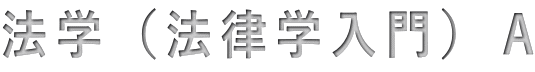法律学科では、4年間でさまざまな法律について専門的に学ぶことになります。しかし、法律を専門的に学ぶためには、知らなければならないことや理解しておくべきことがたくさんあります。本講義は、法律学科に入学したばかりの法律初学者対象の入門講義として、一見堅苦しくて近づきがたく思われる法律を理解するための基礎となる知識を具体的に解説していきます。これから学ぶことになる法律の専門諸科目を正しく理解するためには、この講義で学ぶ基礎知識が必要になります。ですので、この講義でマジメに学べば、社会人として必要な社会常識としての法の知識を習得できるのみならず、法律学科の学生として求められる必要不可欠の基礎を獲得することができます。何より、2年生以降に学ぶ法律の専門諸科目の授業を安心して受けることができるようになるでしょう。
(1) 法律専門科目を専門的に学ぶ上で必要不可欠となる法の基礎知識を正しく説明できる。
(2) 法律学習に求められる法的思考を確実に修得して、ものごとを論理的に表現できる。
(3) 法的思考に基づいて、法の基礎的な概念や理論を詳細に解説できる。
教科書と配付資料にもとづく講義形式で行います。わかりやすく理解してもらうために、スクリーンに図解資料などを提示しながら進めます。またDB manabaやresponを活用した双方向型授業方式も取り入れ、アンケートへの回答や意見などについては、適宜フィードバックしていきます。試験の回答例については、実施後にDB manaba上で公表いたします。
(1)DB manabaなどに掲載された次回分の講義資料や関連配付資料に目を通す。講義の予定を確認し、教科書の該当箇所を事前に読んでおく。
(2)講義の内容について、教科書・講義資料や関連配付資料を確認して、授業で扱われた内容を自分で整理してみる。
(3)講義で扱った内容に関して、教科書の関連する箇所の練習問題を解く。
(4)法学検定試験などの資格試験の練習問題と解説をDB manaba上に掲載することがあるので、その問題を解いて、解説に目を通す。
(5)科目「現代社会と法A」で出された課題をもれなく全部こなして、提出物を必ず提出する。
竹下賢 他編 『入門法学 第五版』(晃洋書房、2018年)
道垣内弘人『プレップ 法学を学ぶ前に〔第2版〕』(弘文堂、2017年)
伊藤正己、加藤 一郎 (編集)『現代法学入門 第4版』(有斐閣、2005年)
その他講義時に適宜紹介します。
筆記試験: 75%
平常点評価: 25% (毎回の出席調査報告の内容に基づく加点 )
(1)本科目は法律学科の必修科目です。法律学科の学生は「法学(法律学入門)B」とあわせて、必ず受講しなければなりません。 法律学科以外の学生は受講できません。
(2)科目「現代社会と法」と連動していますので、本講義で「現代社会と法」についての話が出ることがあります。注意してください。
(3)講義には、法律学科の指定する「六法」を必ず持参して下さい。
(4)何らかの事情で欠席する場合には、事前・事後問わず申し出て下さい。出席調査にきちんと反映させます。
(5)講義中の私語は、他の受講生の迷惑になりますので、慎んで下さい。携帯電話の使用は禁止いたします。どうしても講義中に教室から退出しなければならない場合や、事情により遅刻した場合には、他の受講生の迷惑にならないよう注意してください。
(1)まじめな話だけだと疲れるでしょうから、たまに息抜きでクイズをします。
(2)法律系の科目では、教科書と六法を必ず授業に持ってくること。これは法律学科の学生の義務だと思ってください。
(3)毎回の講義資料や、授業で使用したスライド資料は、すべてDB manabaとこのページに掲載します。
(4) DB manabaとresponの使い方については、授業時に説明します。