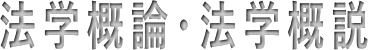テレビや新聞などで、法に関する話題がよく取り上げられます。でも、いざ法について勉強しようと思うと、やはり難しそうだと感じる人も多いでしょう。本講義では、法律学科以外の学生を対象に、一見難しそうにみえる法を理解するための基礎知識を、具体的事例にもとづいてわかりやすく解説していきます。社会人として必要な社会常識としての法の知識、さらには教職志望者が教員として生徒に法を教える上で基礎となる知識、これらの知識を学ぶことがこの授業の目的です。そして、この授業において法を学ぶことで、社会の現実を正しく把握し、判断することのできる感性を身につけて欲しいと考えています。
(1) 社会人として必要な社会常識としての法の基礎知識(教職志望者の場合は、教員として生徒に教える上での法の基礎知識)を正しく説明できる。
(2) 法的に物事を考えるための思考方法を身につけて、法制度上の様々な概念を、教材や資料などを用いて解説できる。
(3) 現代社会における法の役割について、自分の意見を交えながら、適切に説明できる。
教科書と配付資料にもとづく講義形式で行います。わかりやすく理解してもらうために、スクリーンに図解資料などを提示しながら進めます。またDB manabaやresponを活用した双方向型授業方式も取り入れ、質問への回答や意見などについては、適宜フィードバックしていきます。試験の回答例については、実施後にDB manaba上で公表いたします。
(1)DB manabaなどに掲載された次回分の講義資料や関連配付資料に目を通す。
(2)講義の予定を確認し、教科書の該当箇所を事前に読んでおく。
(3)講義の内容について、教科書・講義資料や関連配付資料を確認して、授業で扱われた内容を自分で整理してみる。
(4)参考文献や講義時に紹介した文献を読む。法律にかかわる内容の新聞記事を読み、ニュースなどを視聴する。
竹下賢 他編 『第5版 入門法学』(晃洋書房、2018年)
道垣内弘人『プレップ 法学を学ぶ前に〔第2版〕』(弘文堂、2017年)
中央大学法学部『高校生からの法学入門』(中央大学出版部、2016年)
その他講義時に適宜紹介します。
筆記試験: 70%
平常点評価: 30% (毎回の出席調査報告の内容に基づく加点)
(1)本講義では法学を中心に説明しますので、憲法についてはあまり詳細に説明できません。ですので、なるだけ「日本国憲法」とあわせて受講するようにして下さい。
(2)何らかの事情で欠席する場合には、事前・事後問わず申し出て下さい。出席調査にきちんと反映させます。
(3)講義中の私語は、他の受講生の迷惑になりますので、慎んで下さい。携帯電話の使用は禁止いたします。どうしても講義中に教室から退出しなければならない場合や、事情により遅刻した場合には、他の受講生の迷惑にならないよう注意してください。
(1)法律の話は、初学者にはなじみがないために、難しく、途中で眠くなってしまうかもしれませんね。私もなるだけやさしく説明をいたしますが、学ぶためには、皆さんのがんばりが不可欠ですよ。
(2) まじめな話だけだと疲れるでしょうから、たまに息抜きでクイズをします。
(3) 毎回の講義資料や、授業で使用したスライド資料は、すべてDB manabaとこのページ上に掲載します。
(4) DB manabaとresponの使い方については、授業時に説明します。